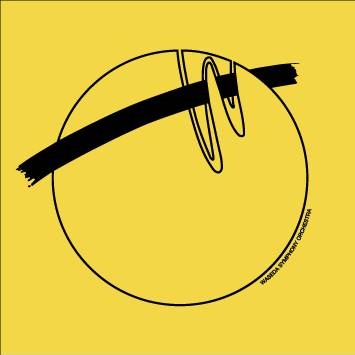リヒャルト・シュトラウスが作曲した交響詩「死と浄化」(Tod und Verklärung)は、1890年に作曲された、彼の3作目にあたる交響詩である。日本では「死と変容」と訳されることが多いが、原題での浄化にあたる語には、好転するといあった意味合いが含まれていることから、我々は「死と浄化」の訳を採用している。
交響詩とは、古典派以前とは異なり、物語を音楽で描写することを試みた様式であって、19世紀初頭にベルリオーズが作曲した幻想交響曲などを皮切りにして、フランツ・リストの「レ・プレリュード」などの名作が続いて確立された形態である。そのような中でも、本作品は人間の生々しくも思える心情が音楽によってありありと描かれており、19世紀後半のドイツ音楽における交響詩の確かな傑作の一つに数えられる。
c-mollの荘厳な雰囲気で曲が始まると、ティンパニによる心臓の鼓動と弦楽器による病人の回顧が描き出される。すると、突然に曲調が変わり、死に対する恐怖から視野狭窄に陥っている病人の、生への執着が表現され、高弦と低弦とのコントラストによって生と死の対立が強調される。その後再び幸福だった日々の懐古のテーマが続くが、死への恐怖が見え隠れする。やがて突如として浄化のテーマが金管楽器によって奏でられると、次第に序奏のテーマに戻り、C-Durの穏やかな雰囲気になる。病人の命は尽きたが、魂は神のもとで浄化を受けたのである。
本作品を作曲した当時、シュトラウスは26歳であったが、彼自身、20歳頃から重病を患い死の淵に立つことがしばしばあった。特筆すべきは、85歳で世を去ったシュトラウスであったが、死を目前にして、昏睡状態から意識を回復した際に、「私が死と浄化のなかで作曲したことは正確だった。」と述べたと言われていることであろうか。生を全うする60年も前から魂の浄化の正確な着想があり、それを音楽に昇華した若きシュトラウスの老熟した感性には驚かされる。
≪参考文献≫
カール・ベーム著、高辻知義訳『回想のロンド』(白水社、1970年5月13日)