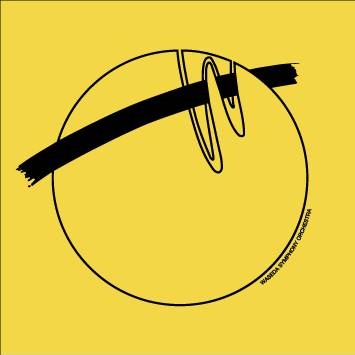若き日のマーラーの苦悩
マーラーの音楽は非西洋的である。と言いきってしまうのは過言かもしれないが、少なくともそれまでの「伝統的な西洋音楽」ではあり得ない、斬新で型破りな響きを持っている。
彼の音楽の「非西洋性」は若き日の「第一歩」であり、彼の作品の中では比較的古典的と評される交響曲第1番でも決して例外ではない。1860年に当時のオーストリア領チェコでユダヤ人の家庭に生まれ、列強国の覇権争いが激化した帝国主義時代に青年期を過ごした彼は、常に自分の出自について思い悩んでいた。彼はよくこう言っていたという。「わたしは、三重の意味で故郷のない人間だ。オーストリア人の間ではボヘミア人として、ドイツ人の間ではオーストリア人として、そして、全世界の中ではユダヤ人として。どこへ行っても招かれざる客で、絶対に歓迎されることはないのだ」と。彼が20代で書いた最初の交響曲(厳密には彼は「第1番」の前に4つほど交響曲の習作を書いているが)から意欲的に「西洋伝統音楽への挑戦」を行っているのには、このようなコンプレックスがあったことも背景にあるのではなかろうか。
若き日のマーラーが悩んでいたのはそれだけではない。1896年、本曲の初演から7年後に彼は友人に宛てた手紙の中で、「(交響曲第1番は)恋愛事件を直接の動機として作曲されたものだ」と記している。このような視点から、ほぼ同時並行で作曲されており、青年の失恋の生々しい心情を表現した歌曲集「さすらう若人の歌」と精神的なつながりを持っているということができる。後述するが、この歌曲集と本曲は音楽的にも関連性があり、第2曲と第4曲の旋律が交響曲にも登場しているほか、後述する「カッコー」の音型も多用されている。このような青春の感情といった点で、例えばマーラーの愛弟子で指揮者のブルーノ・ワルターは著書でこの曲を「マーラーのウェルテル」だと強調している。ゲーテの「若きウェルテルの悩み」と共通するものがそこにあるというのだ。
標題について
この曲は初演からしばらくの間は「交響詩」とされており、現在では削除されてしまった第2楽章「花の章」を伴った2部構成の全5楽章構成だった。1892年のハンブルク稿では各楽章に特に細かい標題と説明文が伴っており、全曲に「巨人」というタイトルが付けられていた。しかし、これらの標題は「巨人」というものも含めて、1896年のベルリンでの演奏の際にはマーラー自身によって全て削除されている。
「巨人」というタイトルは彼の青年時代からの愛読書であるジャン・パウル同名の小説からとられている。この小説は1803年に書かれたもので、天才的で奔放な人間アルバーノが、恋愛をはじめとする多くの人生経験を積んで人間として成長する過程が描かれている。当時のワイマール宮廷や天才主義・巨人主義といったものを批判する思想も織り込まれている。つまり、マーラーのつけた「巨人」というタイトルは決して巨人主義礼賛ではないのだ。また、小説のストーリー忠実に描写しているわけでもない。あくまで若き青年の豊かな感情や狭い世界での戦い、必死になって自らの人生に立ち向かう姿を想起させるものとして付けられたものだったのだ。彼はこの標題が聴衆に誤解を与えるものだと考え、削除したのである。
各楽章解説
第1楽章
当初は「春、そして終わることなく」という標題がつけられていた。序奏付きのソナタ形式をとっている。「冬の長い眠りからの春の目覚めを描写している」という序奏では、微睡むような静けさの中で目覚めを象徴するかのような下降四度の「カッコー」の音型のファンファーレが演奏される。スコアには「自然の音のように」と記されており、冒頭の弦楽器の7オクターブにもわたるAの音の響きは、天空や自然、悠久の自然、時空の無限の拡がりを想起させるようだ。ファンファーレの四度というのは、世界中多くの民族の民謡で音階の柱となっている音でもある。どちらも西欧以前、あるいは非西洋の世界への親近性を感じさせるもので、西洋音楽に付き物のドミソの和音の姿はここでは見られない。第1主題は「さすらう若人の歌」の第2曲「朝の野原を歩けば」の旋律が登場する。この歌曲における「この世界が大好きだ!」というテクストはこの楽章において象徴的である。展開部では序奏が回帰した後再び明るくなるが、少しすると唐突に不穏な雰囲気を呈する。これは最終楽章におけるフィナーレの予兆であると同時に、終楽章の「地獄」が既に影を落としていることの表現である。盛り上がって頂点を築くと再現部に入り、速度を上げて短いコーダの後に終わる。
第2楽章
当初は「帆をいっぱいに張って」という標題がつけられていた。曲としては3部形式をとる。ドイツの田舎風の踊りであるレントラーとワルツが掛け合い、4種類の異なった踊りの旋律が登場する。トリオに入ると牧歌的な雰囲気になり、ゆったりと曲が進む。
第3楽章
当初の標題は「座礁して!(カロ風の葬送行進曲)」であった。「カロ風」というのはベートーヴェンと同時代作曲家・作家・画家等多彩な才能を持ち、マーラーが高く評価していたE.T.A ホフマンの「カロ風幻想小品集(Fantasiestücke in Callots Manier)」という文学作品に由来している。この作品集はホフマンが偏愛していた戯画作者ジャック・カロ(Jacques Callot)の名をつけて4巻本で発行され、作品集の序文はジャン・パウルから寄せられていた。ジャック・カロは「聖アントワーヌの誘惑」という作品で美女や悪魔に戯画化された欲望と戦いの場面を版画にしており、ホフマンはそのような幻想的な世界を好んでいたようだ。また、「葬送⾏進曲」というのはモリッツ・フォン・シュヴァントのエッチング『狩⼈の葬列』に由来していると言われている。このエッチングは死んだ狩⼈が、⾃分が殺そうとした動物に弔われるというとても⽪⾁なものである。
冒頭のカノンの旋律は重々しい葬送行進曲のように思えるが、雰囲気はすぐに変化し、俗っぽくなったり、感傷的になったりする。「この世の野蛮さ、滑稽さ、卑俗さが、葬送の音楽に混じってこえてくる。」というマーラーの説明からも理解できるように、この楽章における多面性は悲劇と日常性とが隣り合わせに存在していることの象徴である。中間部では「さすらう若人の歌」の第4曲の中間部「道端に一本の菩提樹が立っていた」による素朴で美しい旋律が使われている。
第4楽章
当初つけられていた標題は「地獄から天国へ」であった。曲は拡大されたソナタ形式である。呈示部では嵐のような導入部の後に、低弦と木管楽器に闘争的な第1主題が現れる。落ち着くと弦による息の長い第2主題が演奏される。感動的な頂点を築いた後、再び冒頭の雰囲気が回帰し、展開部となるが、すぐに明るくなり、「勝利」の動機が弱音で演奏される。
その後、またもや墜落して冒頭の募囲気が戻るが、再び「勝利」の動機が今度は堂々と現れる。マーラーは第4楽章について、「再三にわたり、勝利のモティーフとともに彼は運命を超越し、それを掴んだかと思いきや、そのたびに運命の一撃をくらい、死においてはじめて、勝利を手中に収めることができる。」と説明している。「地獄」と「勝利」の目まぐるしい表現はまさにこの「闘争」を表現していると理解できる。マーラーが「青春時代の回想」と呼んだ第1楽章再現の後、曲は再現部に入り、まず第2 主題が再現される。盛り上がった後に、弱音で第1主題の再現がされるが、曲はいよいよ「最高の力で」と指示されたフィナーレに突入し、3度目の「勝利」の動機とともに、天国のコラールを演奏する。
≪参考文献≫
音楽之友社編(1992年)『マーラー』音楽之友社 〔作曲家別名曲解説ライブラリー①〕
コンスタンティン・フローロス著 前島良雄・前島真理訳(2005年)『マーラー 交響曲の全て』藤原書店
柴田南雄(1995年)『グスタフ・マーラー ―現代音楽への道―』岩波書店
金聖響/玉木正之(2011年)『マーラーの交響曲』講談社
金子建志(1994年)『こだわり派のための名曲徹底分析 マーラーの交響曲』音楽之友社
岩下眞好(1995年)『マーラー その交響的宇宙』音楽之友社
根岸一美/渡辺裕 監修(1993年)『ブルックナー/マーラー事典』東京書籍